
ガーデンパレット・イメージ
ガジュマル(学名:Ficus microcarpa)は、東南アジアから南アジア、オセアニアの熱帯から亜熱帯地域を原産とする常緑樹です。日本では沖縄に自生しており、温暖な気候を好む植物として知られています。
ガジュマルを屋外で育ててみたいと考えているものの、どのように管理すればよいのか悩んでいませんか。室内で育てる観葉植物というイメージが強いガジュマルですが、実は条件が合えば屋外でも元気に成長させることができます。ただし、屋外での育て方には室内とは異なる注意点があり、特に初心者の方は水やりや冬の管理、剪定のタイミングなどで失敗や後悔をしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、ガジュマルの育て方について屋外栽培に焦点を当て、初心者でも安心して取り組める具体的な方法を解説します。季節ごとの管理方法や、室内との使い分けについても触れていきますので、これからガジュマルを育てようと考えている方はもちろん、すでに育てている方にも役立つ情報が満載です。
この記事を読むことで以下の内容が理解できます。
- ガジュマルを屋外で育てる際の基本的な管理方法
- 季節や環境に応じた正確な水やりと温度管理のポイント
- 冬越しの方法と室内への移動タイミング
- 剪定や病害虫対策など長期的なケアの方法
ガジュマルの育て方|屋外での栽培ポイント

ガーデンパレット・イメージ
- 屋外での育て方の基本
- 初心者でも失敗しない置き場所
- 水やりの頻度とタイミング
- 剪定の時期と方法
屋外での育て方の基本
ガジュマルを屋外で育てる際には、まず植物の基本的な性質を理解することが重要です。原産地は東南アジアなどの温暖な地域であり、高温多湿の環境を好みます。日本国内では温暖な地域、具体的にはUSDA耐寒性ゾーン10〜12相当の気候、つまり南西諸島や一部の南九州地域であれば屋外での通年栽培が可能となります。
屋外栽培の最大のメリットは、十分な日光と自然の風通しを確保できる点にあります。室内では光量が不足しがちですが、屋外なら光合成が活発に行われ、葉の色艶も良くなるでしょう。また、風通しが良いことで病害虫の発生も抑えられます。
ガジュマルは耐暑性が強い一方で、耐寒性はやや弱いという特徴があります。安全な運用目安は最低気温10℃以上です。短時間でも5℃付近まで下がる予報が出たら室内退避を推奨します。霜や寒風は絶対に避けてください。
屋外で育てる場合は、鉢植えでの栽培をおすすめします。温暖地で地植えにすると将来的に大型化し、根系が強く伸びて舗装面の持ち上がりや配管への影響といったリスクが生じる可能性があります。鉢植えであれば季節に応じて場所を移動でき、管理がしやすくなるでしょう。
土は水はけの良い観葉植物用の培養土を使用します。市販の観葉植物用培養土で問題ありませんが、自分で配合する場合は赤玉土6:腐葉土3:軽石1の割合で水はけを重視した配合がおすすめです。排水性が悪いと根腐れの原因となるため、鉢底には鉢底ネットを敷くことを推奨します。鉢底石は必要に応じて薄く入れることで排水性が向上しますが、排水性は主に用土の配合と鉢の穴の設計によって決まります。鉢の素材は通気性の良い素焼き鉢やテラコッタ鉢が適していますが、プラスチック鉢を使う場合は排水穴の管理をしっかり行いましょう。
植え替えのタイミング
ガジュマルは1〜2年ごとに植え替えが必要です。春の気温が安定した後から初夏にかけてが適期となります。根詰まりのサインとしては、水やり後の排水が悪くなる、鉢底から根が飛び出す、土の乾きが異常に早くなるなどが挙げられます。このような症状が見られたら、早めに植え替えを検討しましょう。
初心者でも失敗しない置き場所
ガジュマル挿し木(4年半)🌿
屋外酷暑の雨ざらしなのに
なんかキミ夏を楽しそうに過ごすよね#観葉植物 pic.twitter.com/93W5F75VRu— じーすけ (@1331G) September 12, 2025
屋外でガジュマルを育てる際の置き場所選びは、成功の鍵を握る重要なポイントです。適切な場所を選ぶことで、初心者でも元気な株に育てることができます。
理想的な場所は、午前中から昼過ぎまで日光が当たり、午後は半日陰になるような環境です。東向きや南東向きのベランダや庭が適しているでしょう。ガジュマルは日光を好む植物ですが、真夏の強い直射日光に長時間当たると葉焼けを起こす可能性があります。
季節別の置き場所
春から初夏にかけては屋外の明るい場所に置きます。ただし、真夏の時期は強い日光と高温、そして急な環境変化が葉焼けの主な原因となるため、遮光ネット(日射を30〜50%程度カットするもの)を使用するか半日陰に移動させましょう。葉焼けした部分は元に戻りませんが、新葉の更新により株全体は回復可能です。
秋は気温が下がり始める時期のため、冬に向けた準備を意識します。冬については後述の専門セクションで詳しく解説しますが、基本的には室内管理が望ましく、温暖な地域で屋外越冬を試みる場合も無霜地帯で風除けがあり、輻射熱が得られる南向き壁面など局所条件が整う場所を選びます。
エアコンの室外機の近くは避けましょう。温風や冷風が直接当たると、葉が傷んだり乾燥しすぎたりする原因となります。また、風通しが悪すぎる場所も病害虫の発生リスクが高まるため注意が必要です。
鉢を直接コンクリートの上に置くと、夏は輻射熱で根が傷み、冬は冷気で根が冷えすぎる可能性があります。ポットフィート(鉢を浮かせて通気・断熱を確保する台)などを使って鉢を浮かせることで、通気性と排水性が向上し、温度変化の影響も和らぎます。
日照不足のサイン
新しく出た葉が薄い、枝が間延びする、葉色が淡くなるといった症状が見られたら、日照不足の可能性があります。置き場所を見直すか、より明るい場所へ移動させることを検討してください。
水やりの頻度とタイミング

ガーデンパレット・イメージ
水やりはガジュマル栽培において最も重要な管理作業の一つです。屋外での水やりは室内とは異なる注意点があるため、正しい方法を理解しておきましょう。
基本的な水やりの原則は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えることです。指で土を触って確認し、表面が白っぽく乾いていたら水やりのサインと考えてください。受け皿に溜まった水は必ず捨てましょう。
固定的な回数ではなく、土の乾き具合を観察して判断することが最も重要です。鉢のサイズや素材、置き場所の日当たりや風通し、気温によって乾燥スピードは大きく変わります。
春から夏の水やり
成長期である春から夏にかけては、土が乾きやすくなります。春から初夏は数日〜1週間おき程度、真夏の屋外では毎日〜隔日になることもあります。特に小型の鉢やテラコッタ鉢を使用している場合は、乾燥が早いため注意が必要です。水やりは早朝か夕方の涼しい時間帯に行います。
真夏の日中に水やりをすると、水が温まって根を傷める可能性があります。また、強い日光と高温、急な直射日光への復帰が葉焼けの主な原因となるため、日中の葉面散水は温度ストレスを助長しやすく避けた方がよいでしょう。
秋から冬の水やり
気温が下がる秋以降は、ガジュマルの生育が緩やかになります。水やりの回数も徐々に減らし、秋は土が乾燥してから数日後、冬は環境により月に0〜2回程度の少量に抑えます。ただし、完全断水は根の乾燥死を招くため危険です。
冬場は乾かし気味の最小限潅水を心がけます。室内で10〜15℃程度を保てる環境であれば、月に1〜2回ごく少量の水を与えてください。屋外の場合、長雨は根腐れのリスクが高まるため軒下に避難させ、雨ざらし放置は避けましょう。土が湿った状態で冷え込むと、根が冷えて致命的なダメージを受ける可能性があります。
葉水(霧吹きで葉に水を吹きかけること)は湿度を保ち、病害虫予防にも効果的です。葉の表裏に水を吹きかけると、葉の艶も良くなります。ただし、葉水は朝に行うのが基本で、夜間や低温時は避けてください。夜間の低温高湿は病気を助長する恐れがあります。
剪定の時期と方法
ガジュマル剪定2回目
購入してまだ1年たたないのだけど、成長早いのね😅
今回も切った枝は棄てません😊 https://t.co/UiyqBdHrTr pic.twitter.com/qoXezN81oQ— KERO🦕 (@KERO22600739) September 28, 2025
ガジュマルは生育が旺盛な植物のため、定期的な剪定が必要です。適切な時期に正しい方法で剪定を行うことで、樹形を整え、風通しを良くし、病害虫の予防にもつながります。
剪定の最適な時期は、成長が活発になる春から初夏にかけてです。具体的には3月下旬から7月頃が適しており、特に5〜6月が最も適した時期といえます。この時期に剪定すれば、切った部分からすぐに新芽が出て回復も早いでしょう。
剪定の基本的な手順
まず、枯れた枝や変色した葉を取り除きます。次に、混み合っている部分や内側に向かって伸びた枝を間引き、風通しを良くしましょう。樹形を整えるため、飛び出している枝や伸びすぎた枝を切り詰めます。
剪定には清潔でよく切れるハサミを使用してください。切れ味の悪いハサミを使うと、枝を傷めて病気の原因となります。また、ガジュマルは切り口から白い樹液(ラテックス)が出ますが、この樹液は皮膚に触れるとかぶれることがあるため、必ず手袋を着用しましょう。
ガジュマルの樹液はペットが誤食すると軽度の中毒症状を起こす可能性があります。剪定枝は子どもやペットの手の届かない場所で処分してください。ペットを飼っている方は、剪定作業中や剪定後の枝の処理にも注意が必要です。
切り口には癒合剤を塗ると、病原菌の侵入を防ぎ、傷の治りが早くなります。剪定後は直射日光を避けた明るい場所に1週間ほど置いて、株を回復させてください。
剪定で切った枝の活用
剪定で切り取った枝は、挿し木として利用できます。挿し木の適期は5〜8月で、この時期が最も発根しやすくなります。10cm程度の長さに切り、下の葉を取り除いて水に挿しておくと2〜3週間で根が出てきますが、鹿沼土やバーミキュライトなどでの土挿しの方が安定して発根します。発根促進剤を使用するとさらに成功率が高まるでしょう。
秋以降の剪定は避けるべきです。冬に向かって気温が下がる時期に剪定すると、株が弱って寒さに耐えられなくなる可能性があります。どうしても剪定が必要な場合は、最小限にとどめてください。
ガジュマルを屋外で育てる際の季節別管理

ガーデンパレット・イメージ
- 春から夏の育て方のコツ
- 秋の管理で注意すべきこと
- 冬の管理と室内外の判断
- 病害虫の予防と対策
- 肥料の与え方
春から夏の育て方のコツ
春から夏にかけては、ガジュマルにとって最も生育が活発になる季節です。この時期の管理がその後の生育に大きく影響するため、ポイントを押さえておきましょう。
春は気温が上がり始め、休眠から目覚める時期です。3月中旬から新芽が出始めたら、徐々に水やりの回数を増やしていきます。植え替えや剪定もこの時期に行うと、株への負担が少なく回復も早いでしょう。
日光管理のポイント
春の柔らかい日差しはガジュマルにとって理想的です。しっかりと日光浴をさせることで、葉が厚く丈夫に育ちます。ただし、冬の間室内で管理していた場合は、急に強い日光に当てると葉焼けを起こす可能性があるため、段階的に慣らしていくことが重要です。
最初は明るい日陰に1週間程度置き、その後午前中だけ日が当たる場所に移動させます。さらに1週間後に日当たりの良い場所へと段階的に移すことで、葉焼けを防げます。
夏の管理で気をつけること
6〜8月にかけての真夏は、ガジュマルが最も元気に成長する時期です。しかし、強すぎる直射日光は葉焼けの原因となるため、遮光ネットで30〜50%程度遮光するとよいでしょう。
前述の通り、真夏の屋外では土の乾きが非常に早いため、毎日〜隔日の水やりが必要になることがあります。朝に水やりをしても夕方には土が乾いている場合は、朝晩2回の水やりを検討してください。ただし、受け皿に水が溜まったままにならないよう、必ず捨てることを忘れずに。
夏は生育が旺盛なため、新しい枝がどんどん伸びます。樹形が乱れてきたら、軽い剪定を行っても問題ありません。風通しを確保することで、病害虫の発生も抑えられるでしょう。
秋の管理で注意すべきこと
ガジュマルの葉が落ちてきたから秋 pic.twitter.com/cu2bxTK8oH
— ぱせりん (@ppppaserinnn) September 27, 2025
秋は夏の暑さから解放され、ガジュマルにとって過ごしやすい季節です。しかし、徐々に気温が下がっていくため、冬に向けた準備を始める大切な時期でもあります。
9〜10月前半までは、まだ気温が高く生育も続きます。引き続き日当たりの良い場所で管理し、水やりも土の乾き具合を見ながら行いましょう。ただし、朝晩の気温差が大きくなるため、急激な温度変化には注意が必要です。
水やりの調整
10月後半になると、気温の低下とともに土の乾きも遅くなります。このタイミングで水やりの頻度を徐々に減らしていきましょう。土の表面が乾いてから数日後に水を与える程度に調整します。
秋は台風のシーズンでもあります。強風が予想される場合は、事前に鉢を安全な場所に移動させてください。倒れて鉢が割れたり、枝が折れたりするのを防ぐことができます。
肥料の打ち切り時期
秋も肥料を与え続けると、新芽が出て冬の寒さに耐えられなくなる可能性があります。9月いっぱいで肥料を打ち切り、10月以降は与えないようにしましょう。肥料を控えることで、株が徐々に休眠モードに入る準備ができます。
秋は病害虫が発生しやすい時期でもあります。葉の裏や幹を定期的にチェックし、害虫を見つけたら早めに対処してください。冬を前に株を健康な状態に保つことが、越冬成功の鍵となります。
冬の管理と室内外の判断

ガーデンパレット・イメージ
冬のガジュマル管理は、屋外栽培において最も慎重を要する時期です。適切な判断と対策により、翌春も元気な姿を見ることができます。
基本的な越冬方針
ガジュマルの安全な運用目安は最低気温10℃以上、短時間でも5℃付近まで下がると葉が落ち始め、枯死のリスクが高まります。多くの地域では冬場の室内管理が基本となります。関東以北では必ず室内に取り込む必要がありますが、南西諸島や南九州など温暖な地域では、適切な対策を施せば屋外での越冬も可能です。
室内への移動タイミング
最低気温が10℃を下回り始める時期が、室内への移動を検討する目安です。天気予報で夜間の気温が10℃以下になる日が続くようなら、室内への移動を検討しましょう。関東地方では10月下旬〜11月上旬、東北地方では10月中旬が目安となります。
室内に移動させる前に、害虫チェックを行いましょう。葉の裏や幹に虫がついていないか確認し、見つけた場合は駆除してから室内に入れます。また、鉢の底や受け皿も洗って清潔にしておきましょう。
急激な環境変化は植物にストレスを与えます。可能であれば、夜だけ室内に入れて昼間は屋外に出すという方法を1週間ほど続け、徐々に室内環境に慣らしていくとよいでしょう。
室内管理のポイント
室内管理の最大のメリットは、安定した温度環境を保てる点です。できるだけ日当たりの良い窓際に置き、定期的に鉢を回して全体に光が当たるようにしてください。ただし、窓際は夜間に冷え込むため、夜だけ部屋の中央に移動させるか、カーテンで冷気を遮る工夫をしましょう。エアコンの温風が直接当たらないように注意してください。
暖房の効いた部屋は空気が乾燥しやすいため、定期的に葉水を与えて湿度を保ちましょう。ただし、葉水は朝に行うのが基本です。加湿器を使用するのも有効です。
屋外越冬の条件と対策
屋外で越冬させる場合は、最低気温が5℃を下回らない温暖な地域に限られます。加えて、無霜地帯で風除けがあり、輻射熱が得られる南向き壁面など局所条件が整うことが絶対条件です。南向き壁面・無霜・風除け・雨避けが揃って初めて現実的といえます。これらの条件を満たせる場合でも、簡易温室やビニールカバーなどで保護することをおすすめします。
ポットフィートを使って鉢底を地面から浮かせ、冷気が直接伝わらないようにしましょう。風よけネットで寒風を遮断することも効果的です。
屋外越冬を試みる際は、株の状態も考慮しましょう。若い株や夏に植え替えたばかりの株は体力がなく、寒さに耐えられない可能性が高いです。少なくとも2〜3年育てて根がしっかり張った株でなければ、屋外越冬は避けた方が無難です。
万が一葉が全て落ちてしまっても、幹が生きていれば春に新芽が出る可能性があります。諦めずに暖かくなるまで見守りましょう。ただし、幹が黒ずんだり柔らかくなったりした場合は、残念ながら枯死している可能性が高いです。
春になって再び屋外に出す際も、段階的に慣らすことが大切です。急に強い日光に当てると葉焼けを起こすため、前述したように徐々に日光に慣らしていってください。
病害虫の予防と対策

ガーデンパレット・イメージ
屋外でガジュマルを育てる場合、室内よりも病害虫のリスクが高まります。しかし、適切な予防と早期発見・対処により、被害を最小限に抑えることができます。
ガジュマルにつきやすい主な害虫には、ハダニ、カイガラムシ、アブラムシ、コナカイガラムシなどがあります。それぞれ特徴が異なるため、見分け方と対処法を知っておきましょう。
主な害虫と対策
ハダニは葉の裏に寄生する小さな赤い虫で、吸汁により葉がかすれて茶色くなります。乾燥した環境を好むため、定期的な葉水で予防できます。発生した場合は、強めの水流で洗い流すか、専用の殺虫剤を使用してください。
カイガラムシは丸い殻のような見た目で、枝や葉に付着します。殻に守られているため殺虫剤が効きにくく、見つけたら歯ブラシやピンセットで物理的に取り除く必要があります。成虫には浸透移行性の薬剤(アセタミプリド等)や、越冬害虫対策としてマシン油乳剤なども効果的です。増えると株が著しく弱るため、早期発見が重要です。
アブラムシは新芽や若い葉に群がる小さな虫です。放置すると葉が変形したり、すす病を併発したりします。見つけたらすぐに水で洗い流し、専用の殺虫剤を散布しましょう。
コナカイガラムシは白っぽい粉のような塊が葉や茎に付着します。増えると植物の成長が著しく悪くなるため、早めの対処が必要です。
薬剤を使用する際は、高温時(概ね30℃以上)や直射日光下での散布は薬害の恐れがあります。特にマシン油乳剤は注意が必要です。夕方〜涼しい時間帯に、ラベルの指示どおり使用してください。
病害虫の予防には、風通しの良い環境を保つことが最も効果的です。定期的な剪定で込み合った枝を間引き、鉢の周りも整理整頓しておきましょう。また、週に1回程度、葉の裏までよく観察する習慣をつけることが早期発見につながります。
病気の予防
ガジュマルがかかりやすい病気には、根腐れ、すす病、炭疽病や葉斑病などがあります。根腐れは過湿が原因で発生するため、水はけの良い土を使い、水やりのタイミングを守ることが予防になります。
すす病はカイガラムシやアブラムシの排泄物に黒いカビが生える病気です。害虫を駆除し、発生した部分は濡れたタオルで拭き取りましょう。症状がひどい場合は、その部分を剪定して取り除いてください。
炭疽病や葉斑病は湿度が高すぎる環境で発生しやすくなります。風通しを良くし、水やりの際に乾湿のメリハリをつけることで予防できます。
肥料の与え方
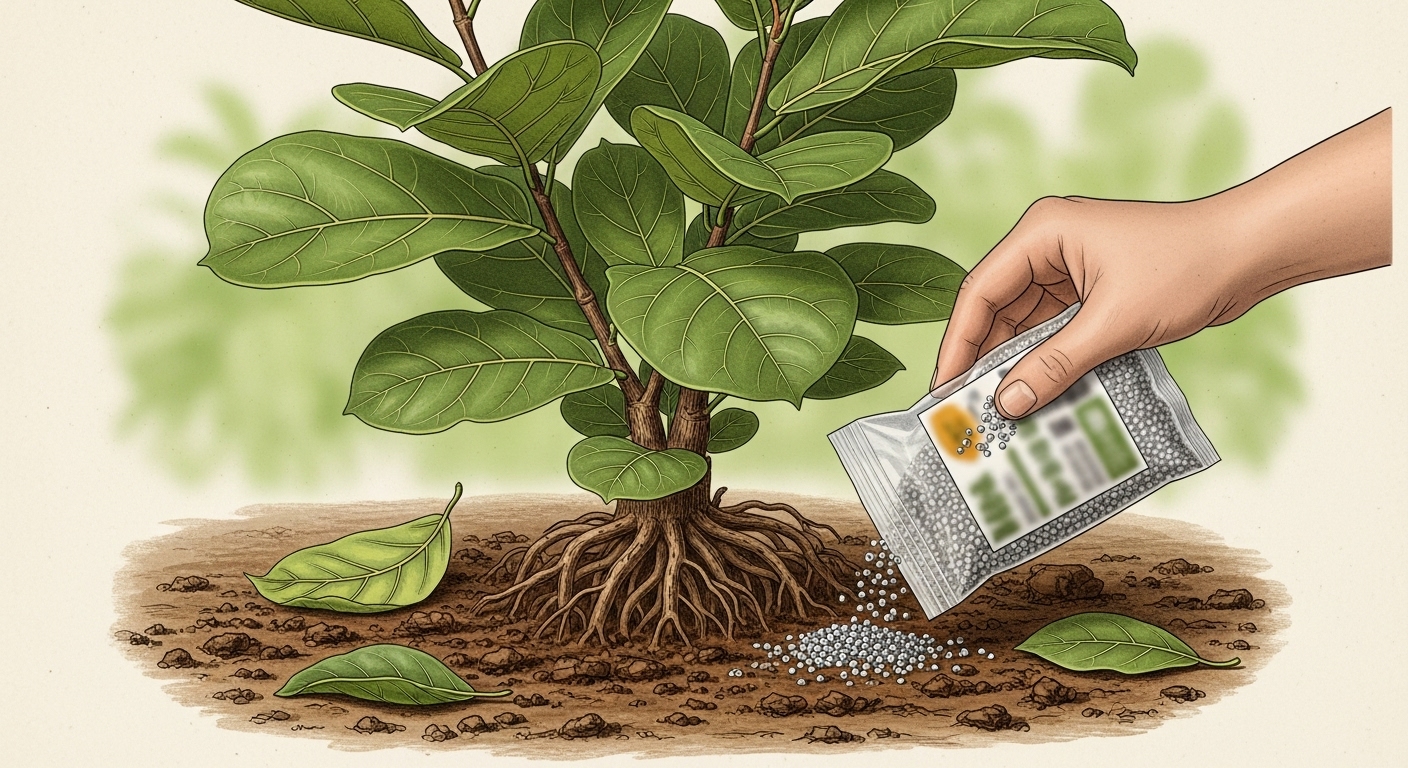
ガーデンパレット・イメージ
ガジュマルを健康に育てるためには、適切なタイミングで肥料を与えることが重要です。ただし、与えすぎると肥料焼けを起こす可能性があるため、適量を守りましょう。
肥料を与える時期は、生育が活発な春から秋にかけてです。具体的には4〜9月までの間に、月に1回程度の頻度で与えます。冬は休眠期のため肥料は不要です。与えると新芽が出て寒さに耐えられなくなる可能性があるため、避けてください。
肥料の種類と選び方
ガジュマルには、観葉植物用の緩効性肥料が適しています。固形タイプと液体タイプがありますが、それぞれにメリットがあります。
固形の緩効性肥料は、土の表面に置くだけで徐々に溶け出し、効果が1〜2ヶ月持続します。手間がかからず初心者にも扱いやすいでしょう。一方、液体肥料は即効性があり、水やりと同時に与えられるため便利です。2週間に1回程度、規定の濃度に薄めて使用します。
| 肥料のタイプ | 特徴 | 使用頻度 | メリット |
|---|---|---|---|
| 固形(緩効性) | ゆっくり溶ける | 月1回程度 | 手間が少ない、効果が長持ち |
| 液体 | すぐに吸収される | 2週間に1回 | 即効性がある、濃度調整が可能 |
肥料を与える際の注意点
肥料を与える前には、必ず土が湿っている状態にしてください。乾いた土に直接肥料を与えると、根が肥料焼けを起こす可能性があります。水やりをしてから、あるいは水やりと同時に液体肥料を与えるとよいでしょう。
また、植え替え直後や株が弱っている時期には肥料を与えないでください。根がダメージを受けている状態で肥料を与えると、かえって株を傷めることになります。植え替え後は少なくとも1ヶ月間、肥料を控えましょう。
真夏の連日猛暑が続く時期は、液体肥料の濃度を通常より薄めるか、頻度を落とすことをおすすめします。高温時の施肥は薬害や塩類集積を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
肥料の与えすぎは、根を傷めたり葉が焼けたりする原因となります。パッケージに記載された規定量を必ず守り、多く与えればよく育つという考えは捨ててください。適量を定期的に与えることが、健康な株を育てるコツです。
有機肥料を使用する場合は、においや虫の発生に注意が必要です。屋外であれば問題ありませんが、室内に移動させる予定がある場合は、化成肥料を選んだ方が無難でしょう。温暖地で秋まで屋外管理を続ける場合でも、9月以降は肥料を控えめにして、株が冬に向けて準備できるようにしてください。
総括:ガジュマルの育て方|屋外・室内の水やりと剪定を初心者向けに解説
- ガジュマルは東南アジア原産で温暖な地域であれば屋外での栽培が可能
- 安全な運用目安は最低気温10℃以上、5℃付近まで下がると危険
- 霜や寒風は絶対に避け、屋外越冬は南向き壁面・無霜・風除け・雨避けが必須
- 屋外栽培では鉢植えでの管理が移動しやすく推奨される
- 置き場所は午前中から昼過ぎまで日光が当たる場所が理想的
- 真夏の強い直射日光は葉焼けの原因となるため30〜50%の遮光が必要
- 水やりは土の表面が乾いたら鉢底から流れるまでたっぷり与える
- 春から初夏は数日〜1週間おき、真夏は毎日〜隔日になることもある
- 冬は乾かし気味の最小限潅水で月0〜2回程度
- 冬の長雨は根腐れリスクがあるため軒下に避難させる
- 葉水は朝に行い夜間や低温時は避ける
- 植え替えは1〜2年ごとに春から初夏の気温安定後が適期
- 剪定は春から初夏の成長期に行い秋以降は避ける
- 薬剤使用は高温時を避け涼しい時間帯にラベル指示を守る
- 肥料は4〜9月に月1回程度与え冬は与えない